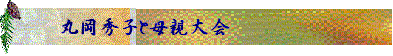 丸岡秀子は、母親大会の“生みの親”とも言われている。 母親大会は、第二次世界大戦後、戦争に反対し平和を願う女性たちの強い願いから誕生した。まず戦後の時代背景と丸岡秀子の働きぶりに注目してほしい。 1950年代、米ソ対立の冷戦構造のなかで核爆弾の開発競争が進み、1954年3月太平洋ビキニ環礁でアメリカが水爆実験を行い、日本のマグロ漁船第5福竜丸が被爆し、乗組員23人が放射能を浴び、ふたたび日本人が核爆弾の犠牲になった。そこで日本では直ちに原水爆禁止運動が起こり、署名運動をひろげ、900万人近くの署名が集められた。同時に「全世界の婦人に当てた日本婦人の訴えー原水爆の製造・実験・使用禁止のために」のアピール文書がつくられ、丸岡秀子は平塚らいてうら6名とともに署名し、国際民婦連本部に送られた。 この年、ベルリンで開かれた国際民婦連書記局会議は「世界の母親が子どもを守るために戦争に反対し、各国の再軍備を防ぎ、友好を深めよう」と世界母親大会の開催を提案した。翌1955(昭和30)年2月9日から5日間、スイス・ジュネーブで世界母親大会準備会が開かれ、47ケ国から婦人団体の代表250人が集まり、丸岡秀子は、高良とみ、羽仁説子、鶴見和子、本多喜美らとともに日本代表として参加した。 丸岡秀子と平塚らいてうの交際は、富本一枝の紹介による。平塚は丸岡秀子の農村婦人問題や生協活動、教育運動における誠実な活動に注目し、ジュネーブの世界母親大会準備会の日本代表にぜひとも参加してほしいと願っていた。しかし当時の丸岡秀子は手術後の身で、医師からも「なるべく安静に」といわれていて、らいてうの要請を何度も断り、富本一枝を通じて辞退の意を伝えていた。ところが平塚らいてうは「雪解けのぬかるみの中を下駄を履いて」世田谷の丸岡秀子の家へ訪れ、「低い優しい声で無理を承知の説得」を重ね、一歩も譲らない強い要請」を続けた。後年、丸岡秀子は平塚らいてうが「いかに信念を崩さない人」かと回顧しているが、富本一枝と平塚らいてうとの“信頼の絆”が強い魂と魂の結びつきであったかも示している。 ジュネーブで行われた世界母親大会準備会-議長は、フランス生まれの科学者ウージェニイ・コットン。物理学者マリー・キューリーの愛弟子で戦時中は反ナチ抵抗運動で二度も逮捕され、戦後は平和運動、婦人運動に献身し世界平和評議会の副議長も勤めていた。このコットンの「世界母親大会のために」と題した演説は1時間10分に及び、人間愛の精神に溢れた格調高い内容で丸岡秀子も感動している。会場では先に提出した「日本婦人の訴え」が配られて反響を呼び、丸岡秀子は「もっとも苦しんでいるものが、もっとも温かくむかえられることを知って安心もし、心からうれしく思った。この私の実感を日本のお母さんたちに持ち帰って、母親大会の準備をしたい」と述べた。最終日には日本から持参した原爆映画「永遠の平和」を高良とみの解説で上映している。 * ジュネーブの準備会から帰国した丸岡秀子、羽仁説子、鶴見和子の3人による報告会は3月8日にまず東京麻布公会堂で開かれ、平塚らいてうは「世界母親大会の前に日本母親大会を開こう」と提案した。これをうけて婦団連、日教組、日本こどもを守る会、婦人民主クラブ、日本生活協同組合連合会など60団体が参加して、直ちに日本母親大会人準備会が結成された。丸岡秀子は、羽仁説子、高田なほ子らと実行委員になり、①日本母親大会の開催に力を尽くす、②世界母親大会に派遣する代表を選ぶ役割も担った。ちなみに富本一枝も日本母親大会の準備段階から参加し、平塚らいてうや丸岡秀子を背後で支えていた。戦後史のなかでも1955(昭和30)年は、とくに記憶すべき重要な年になった。
丸岡秀子の「人を見る目の確かさ」を伝えるエピソードだが、母親大会の産みの親としての働きも、農業・農村問題や女性問題に精通している「生身の論理」による裏づけがあつてのこと。同時に平塚らいてう、富本一枝らの友情と信頼の絆の強さも銘記しなければならない。 (解説 寺澤 正) |