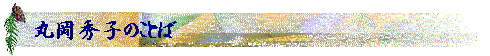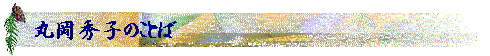生は寄なり、死は帰なり・・死生観
◆「生は寄なり、死は帰なり」という。ここまで、心定まれば、何もあわてることはあるまい。しかも、天寿とは、その人に属する生の終りであって、誰にもあてはまる寿命の目安でもあるまい。しかし、人生の余白は、誰のものでもある。(『いのち、韻あり』八頁)
◆わたしは、ゲートボールも、シルバー・ツアーもいいけれど、年寄りだからといって、生きた社会から外れることのないよう、社会でも、家庭でも、自分の居場所をしっかり持ったらどうかと提言してみた。それが、一番のボケ対策だと、医者も、カウンセラーも、例外なく言っているんだから、ひとつ頑張りましょうや、というわけである。(「宇和青果農業協同組合」一九八五・八・九)
◆蕫大往生﨟という言葉がある。これは、文字通り、「生に往く」であって、「死に往く」ではない。「りっぱな御最後でした。大往生でした」というのは、死者への賛辞だが、その蕫死﨟に対して「大往死」でなく、なぜ、「大往生」なのか。なぜ、「生に往く」の字を当てるのか。シルバー社会の意識の深層は、何よりも健康問題にかかわり、さらに、もし最後がくるなら、だれにも面倒をかけないで、見苦しくなく、りっぱなものでありたい。(『いのち、韻あり』二頁)
◆余白時代とは何か。自由とは何か。真の自由とは、「己に克つことだ」と、若いときに読んだロランの言葉がある。それは身に沁みて、忘れることができない。とすると、好き勝手にふるまうことでないことはもちろんのこと、また、もう年寄りましたからと、何事にも消極的になることでもない。どのように余白の自由を充実させるか、という、自分らしい積極性を引き出すことではなかろうか。(『いのち、韻あり』二八頁)
◆死は、人間誕生のとき、すでにその生命に内包されているものである。かならず何十年かすれば、誰もが見せる現象だし、行きつく場所である。それは二度とない。だから、一生というのではないかとも思う。(『声は無けれど』六二頁)
◆「苦労を泣かせるな」……この言葉の中身は深く、強い。そのことを学んだのは、苦しみのエネルギーの重さを知らされていたからだろう。楽々とした人間のエネルギーは弱い。苦しみのエネルギーは、苦しみを打ちのめす力を持っている。負を正にきたえ直す力を出すことができる。(『声は無けれど』七一頁)
◆個の痛みから人間の痛みへと。また、相手の痛みを自分の痛みへと。(『声は無けれど』九九頁)
◆彼の生きた精神は、それぞれのなかに、火花のように散って火種をともし、この瞬間からそれぞれのなかに生きた。それを信じさせる死でした。わたしは蕫埋葬を許さぬ人﨟としてわたしのなかに井田麟一をかかえこんで生きてきたように思えるのです。生き方は死に方であり、死に方はまさに生き方であることを見事に学ばされました。(『文化評論』1971・9)

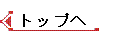
|