 生母と死別した後の少女期、丸岡秀子は浅間山の麓で母方の祖父母の家に預けられ、稲作と養蚕に追われるきびしい小農の暮らしを体験した。"育ての母"となった祖母からは「苦労を泣かせるな。自立できる技を身につけよ」と教えられ、その祖母の写真をいつも持ち歩き、祖母に話しかけるようにして自分の思想を育てていった。<婦人問題の基底には農村婦人の問題が横たわっている。この問題を抜きにして、おろそかにして婦人問題を語れない>(『農村婦人の生活と意見』初出1985)という認識も、いのちを育てる「農」の現場の苦しさを熟知していたからで、とかく村のしきたりのなかで沈黙しがちな農村女性には、事ある毎に<女こそペンを持とう>と訴えてきた。
丸岡秀子自身が「書くこと」に目覚めたのも、祖父母と暮らしていた少女期の日々で、さまざまな差別や矛盾に心を痛め、その<痛み深く、傷大きく、それを重ね重ねることが長いほど、大切なエネルギーが蓄えられる>のを知り、書くよろこびと同時に書く怖さも知ったという。しかも<物を書く場合、もっとも大切なことは自分が何を言いたいのかを知ること>であり、<どのように書けば読む人にわかってもらえるかという技術というか、やり方を考えること>だと述べて、書くことが<結局、最後はわたし自身の生きる姿勢ではないか、どのように自分の一生をつくるかということ>(『女の階段』1978刊・序文)なのだと説いている。
日本農業新聞に「女の階段」という投書欄が設けられたのは1967年夏。この投書欄から農村女性の間に「回覧ノート」が生まれ、70年代以降、丸岡秀子の励ましもあって「書くことで考え、行動し、連帯する」農村女性たちの環が全国にひろがっていた。
丸岡秀子の没後、生まれ故郷長野県臼田町の稲荷山に有志の手で記念碑が建立されたが、そこには「読むこと、書くこと、行うこと、秀子」と刻まれている。また、農協婦人部の代表は没後一年目の偲ぶ会の席上、丸岡秀子の生きかたと助言が<いま、日本の農業を支えている三百四十万の農村婦人の心に大きな灯火をともした>と謝辞を述べていたが、とくに農の現状を「書く」ことで結びあう農村女性の行動は、それぞれの地域の農業農村に変化をもたらす新しい火種ともなっている。
(解説 寺澤 正)
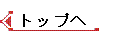
|
