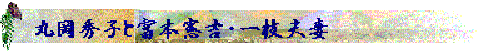 ―奈良の学生時代に、ほとんど家族の一人のように、出入りさせていただいたのは、大正十年のことである。富本さん夫妻が、安堵村に工房を作ってから、数年後の事だったろうか。― この出会いが丸岡秀子に大きな影響を生涯与え続けた。 ―わたしにとって、富本夫妻は、「近代とのめぐり合い」そのものだった。― 雑誌に掲載された一枝の詩を読んで感動した奈良女高師二年生の秀子は、だれの紹介もなく安堵村の工房「つちや」を訪ねる。そこで一枝から陶工である夫の富本を紹介される。その頃一枝は、子育てをしながら、『婦人公論』『婦人の友』『女性日本人』、さらには『女性同盟』『中央公論』などに詩や随筆、小説を精力的に執筆していた。この夫婦の生活にかって秀子が見たこともない、解放された人間の暮らしを身近にみた。互いの自己主張があり自由と平等があった。生まれて初めてコーヒーを飲み、バッハやベートーヴェンやショパンの名前を知った。一枝の書架から多くの書物を借り出して読んだ。トルストイ、ドストエフスキーの作品から、ロマン・ロランやルソーなどを次々によみあさった。また有島武郎、長与善郎など白樺派の作品も手にした。富本が窯出しをする日が日曜日に当るときは、いつも手伝った。 ―陶芸家ではなく、陶工といい続けた人の面影が、「つちや」と共に浮かんでくる。土を運び、薪を選び、一晩中火の番をして過ごした翌朝の疲労し切った顔は、まさに陶工の顔であった。― 最晩年の著書二点 (岩波書店) (『陶工・富本憲吉の世界』/成澤むつ子著『自立の開拓者 丸岡秀子』より引用) (解説 稲葉 通雄) |