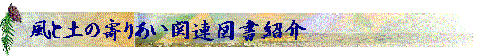
過去と現在のあかしを問い、生きる勇気を得る 松本昌次(編集者) 『ある愛のかたち』は、稲葉有さんにとって、『矢ぐるまの花』(青娥書房)以来、実に二五年を距てての小説上梓という。感慨ひとしおのものがあろう。わたしにも、深い個人的感慨がある。 『矢ぐるまの花』について、わたしはかつて、小林秀雄の『モオツァルト』のなかの言葉を借り、「この作品には"走る悲しみ"がある」と評したことがある。小林秀雄は、スタンダールとアンリ・ゲオンの評言をもとに、「モオツァルトのかなしさは疾走する。」といっているのだが、なぜか、稲葉さんの小説を読んだ途端、二〇代はじめに読んで感銘を受けたこの言葉が、不意に強くわたしには想いかえされたのだった。そして、『ある愛のかたち』を読み了えたあと、その想いはますます深まるかのようである。 それは、小説といっても、主人公の「私」の現実生活でのさまざまな悲痛な経験が作品の骨格をなしていて、それらのいくつかの局面に、時には至近距離からわたしは接したことがあったからでもある。特に、一九九三年夏、入院してわずか四八日で急逝した「妻のミツコ」さんには、格別の想いがある。小説で描かれている「私」のひきおこした女性問題での、「ミツコ」の深刻な苦悩と悲哀を、いまもわたしはありありと想いおこさずにはおれないからである。そして、長男「ユウ」の妻「フーちゃん」の、幼児二人を残しての三六歳の死と、その両親の相次ぐ死。この小説は、いわば、事実としての近親の死者たちの記憶をとおしての「私」の再生と鎮魂の物語である。 「私」に再生と鎮魂の道をさし示すのは、「あなたをママ(ミツコ)のところに連れていってあげるまで、面倒を見てあげる」という、生前「ミツコ」と親しかった「尚子」である。「尚子」の夫「ゾウさん」も、二歳の「れい子」を残して世を去っている。「一緒に暮らしさえしてくれれば」という「私」のことばで、ある日、犬の「バロン」と「尚子」は家にやってくる。そして、「私」と「尚子」の日常と、さまざまの旅がはじまる。旅は、年末をすごす横浜のホテルと鎌倉、上海・桂林・蘇州の五日間、岡本太郎の《太陽の塔》だけを残した日本万国博覧会の跡地、軽井沢、さらに遠くフランス・モナコに及ぶ。その道すじで「私」は、死者「ミツコ」への断ち難い記憶と、生者「尚子」のかえがたい存在を往還し確認することで、みずからの過去と現在のあかしを問い、生きる勇気を得るのである。 ここで、この小説に重要な世界を提示するのが、軽井沢を舞台にした円地文子の小説『彩霧』であり、「尚子」が導いてくれた「夢幻能」である。前者は、「ミツコ」と、彼女を悲しませた「女性カメラマン」との性愛が刻印された軽井沢の、「妖しい淫靡な魅力」であり、後者は、「あの世もこの世も区別のない」、いわば「ミツコ」を傍に感じる「夢幻体験」である。「私」は、『彩霧』によって、人間にとっての"性"の頸木に思いを馳せ、「夢幻能」によって、「シガントヒガン、ゲソセイトメイカイノ、サカイモナイ、『ムゲン』ノセカイ」に到達するのである。 この小説は、極めて"私小説"的告白スタイルをとりながら、小説・詩・能・美術・建築、そして街の風景などに対する芸術批評が至るところにちりばめられていることも特筆すべきで、稲葉さんの芸術的資質を示すものであろう。また、もともとは、稲葉さんも参加する同人誌「新現実」に、「夢幻泡影(むげんほうよう)」のタイトルで連載されたものである。単行本にあたって、「ある愛のかたち」と改題されたとのことだが、「私」は「ミツコ」の墓へ、「尚子」は若くして死別した「ゾウさん」の墓へ、それぞれが骨を埋めるまで、それぞれの死者への絶ち難い記憶を胸に抱いてお互いの愛に生きる"かたち"に、わたしは、あらためて"走る悲しみ"を覚えざるを得なかった。 前著同様、カバーと口絵の風間完氏の画は静謐で美しい。 稲葉
有 著 『ある愛のかたち』 書評 亡妻と現在の妻との同化 寺田 博(文芸評論家) この小説は一口にいって、亡妻を追慕する心境にある男の、現在の愛妻との暮らしを綴った中編小説である。書きようによっては、鼻持ちならない作品になりかねない主題を、決してそうはならない作風によって、佳作に仕上げたのは、作者の対象に対する距離のとりかたと、老いを迎えた自己への省察が行き届いているからだろう。 作者とほぼ等身大の〈私〉は、一九九九年の大晦日を現在の妻と産休中のその娘が産んだ九ヵ月の赤ちゃんを連れて、磯子台のホテルヘ出かけるところから始まる。妻と娘といっても、本人の希望で入籍していない妻と、妻が亡夫との間に産んだ娘であり、その娘の赤ちゃんだから、縁の薄い関係ともいえるが、互いに仕事を持つ身なので、カウントダウンのパーティがあり、おせち料理の用意されたホテルヘ宿泊にきたのである。 七年前に最初の妻が膵ガンで亡くなった年には、〈私〉は、二人の息子夫婦に孫たちと下田の温泉宿に出かけた。妻の写真を部屋のテレビの横に置いて、片時も視界からはずさなかったという。これは現在の妻との暮らしのなかにも持ち込まれており、夕食の折も、座卓に並べられた料理の器の間に、亡妻の写真を置くのである。 そもそも現在の妻は、亡妻が経営していたブティックの客で、何かと相談を持ちかけるような親密な間柄だった。〈私〉と現在の妻は、妻の死後、半年ぐらいたってから「一緒に食事をしませんか」と〈私〉が誘ったのがきっかけで、「一緒に暮らそう」になり、亡妻の三回忌のあと、二人だけで教会に行って、結婚した。彼女は「あなたの奥様は、ママひとりでいいの。ママによくしてもらったから、お返しをするのよ」といって、入籍を拒んでいる。そういう現在の妻は、中国旅行で寒山寺に出かけたとき、住職が色紙の為書に「夫婦参拝記念」と書くと、「ママに済まないわ」と呟いて不機嫌になったりする。 〈私〉のほうも、かつて亡妻と出かけたことのある花見の場所や、大阪万博の「太陽の塔」を背景に、現在の妻を立たせてカメラのファインダーをのぞく。亡妻と現在の妻が重なって見える。そしてついに〈私〉は、自分の死に際して、自分の骨壷とは別に、亡妻の骨と自分の骨を混合して指定の壷に納めるよう、遺言書を書くに至る。現在の妻に「大丈夫よ、うまくやるから」といわれて、〈私〉は救われた思いがする。 この私小説ふうの妻との物語は、息子の嫁のガン死やその両親の同日の死などの挿話をふくみながら、主として外出先を舞台として描かれる。北鎌倉、大阪、軽井沢、中国、南フランスというふうに。いわばハレの場所に現在の妻との生活をさらすことで、失われた亡妻との時間を補っているようにも読める。終章に、フランクフルトの店で、骨壷として蓋つきジョッキを購入する場面が描かれ、読者も節目を大事にする〈私〉への共感を禁じえない。 ★いなば・ゆう氏は作家。本名 稲葉通雄。法政大中退。著書に「矢ぐるまの花」「本、それは命あるもの」「本の想い 人の想い」など。一九三三(昭和8)年生。 |
