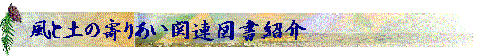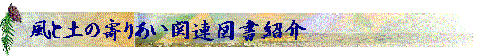書評:婦人民主新聞第2562号(1999/7/15)より『三代の男たちと丸岡秀子』寺澤
正 著
ふたたび悪夢のような時代の足音が間近にせまってくる不安をどこかで感じる。「戦後」を生きているつもりがいつのまにか時計の針が一回りして、又「戦前」の時間を生きることになったような嫌な予感。
命はあっても、それと同じくらい大切な思想や言論の自由が封殺されていった時代。その動きを「いまのとき」と対比しつつ語れる人は少ない。
戦中を知る著者は、国家に刺されたともいえる三人の男たちの生き様を明治、大正、昭和の歴史を軸に、詩的な文体で丹念な織物のような評伝にまとめあげている。
二葉亭四迷、丸岡秀子、田村俊子、といった名前が身近な世代は、自身の思いと著者の言葉を反芻しながら読めるだろう。
教科書でしか知らない戦無派も、軍事一色に染まる時代の動きの怖さと息苦しさを、現在進行形の動きに重ねて読むことができる。
(束)
書評:大窪一志・フリーランサー
『三代の男たちと丸岡秀子』寺澤
正 著
魂でつなぐ近現代史
本書は、三代の男たちと一人の女の評伝であり、それを通した日本近現代史でもある。だが、評者を打ったのは、そこに脈打つ魂のつながりである。肉体は滅びるが、魂は継起していく。
一九三二年前後、非常時共産党で地下活動に従事、逮捕されて二七歳で病死した井田麟一。麟一の父で、二葉亭四迷の弟子、日本ロシア語学の草分けの一人、上海の東亜同文書院と並び称されたハルビン学院の創設者である井田孝平。麟一のおいで、五二年、血のメーデー事件の渦中、二十一歳で警官隊に殺された法大生、近藤巨士。そして、若き寡婦として早大生、麟一を止宿させたことから、これら三代の男たちとかかわりを持ち、彼らの魂を自らの魂と重ね合わせた一人の女、丸岡秀子。
丸岡は麟一の死に対して言う、「埋葬を許さず」と。「わたしは彼を自分の中に生かし、彼はわたしのなかで自分を生かしている」。このように魂は継起していく。
井田孝平はファシズムへの道を開いた陸軍皇道派、真崎甚三郎らを薫陶し、麟一はスパイMに操られた共産党で銀行ギャング事件に帰結する非常手段にまい進し、巨士は後に極左冒険主義とされる戦後共産党軍事方針の下でてい身した。しょせんは左右の全体主義と言われるかもしれない。
だが、彼らの内面を律していたのは、孝平の場合、武士の息子としての儒教理主義であり、麟一の場合、詩人としての魂の純粋性であり、巨士の場合、哲学徒としての「実践生=自由」への希求であった。共通しているのは人生に対するきまじめさである。
彼らの魂のありようをもって彼らの活動を正当化できないのと同じように、彼らの活動のありようをもって彼らの魂を否定することはできない。ここに、キルケゴールの言う「結果としての真理」ではない「過程としての真理」を見ることができる。
今日の日本の没落は、こうした魂の継起が途絶えつつあるところから始まっているのではないか。
(大窪一志・フリーランサー)
|